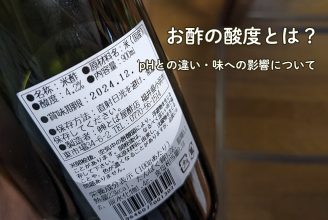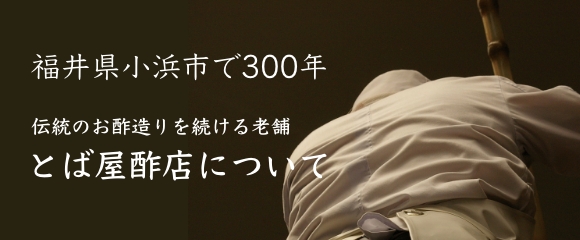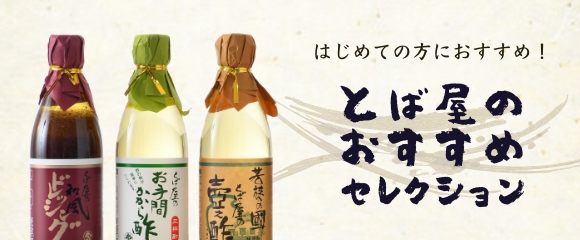すしの歴史とお酢のかかわり

お酢を使った和食といえば、まずはお寿司という方も多いことでしょう。私たちが親しむお寿司は、酢飯と魚を組み合わせた食べ物で、江戸前の握り寿司、海苔巻きずし、五目野菜を混ぜ合わせた散らし寿司など、さまざまな形があります。
しかし、すしの歴史をさかのぼると、はじまりのお寿司には、酢は必要ではありませんでした。今回は、お酢がすしの歴史にどのように関わってきたのかをテーマにお伝えします。
すしの起源は東南アジアの保存食
すしの起源は、東南アジアの川魚の保存食だと考えられています。タイやラオスなどの東南アジアでは、1年の半分が「雨季」と言われる雨の多い季節です。雨季には、あたり一面が海のように水浸しになり、たくさんの魚を獲ることができます。そして、残り半分の「乾季」では、乾燥して水がなくなり、魚が獲れなくなります。
魚は貴重なタンパク質源です。魚の獲れる季節に偏りがあるからこそ、雨季に獲れすぎた魚を保存しなければなりません。まずは魚を塩漬けにし、やがて、ごはんを一緒に漬け込んで発酵させるようになりました。こうして作られた乳酸発酵の保存食が、はじまりの「すし」です。

当時は塩も貴重だったはず。ラオスは内陸国で、海から遠く離れているのに、塩には困っていなかったんですか?

実は、ラオス国土の一部を含むインドシナ半島内陸部には、東南アジア最大の岩塩層が存在します。乾季になると、塩をつくって、発酵食品づくりに活用してきたそうです。
タイで「プラーソム(酸っぱい魚)」、ラオスでは「ソムパー(酸っぱい魚)」と呼ばれるこの発酵食品。実は、現代日本でも作られ続けている滋賀県琵琶湖のフナずしと同じ「なれずし」です。なれずしは、保存性を重視した貯蔵食で、酸っぱくなった漬け床のごはんは捨てて、魚だけを食べます。
日本のすしのはじまりは、東南アジアの川魚の貯蔵法が、中国を経て、稲作と一緒に伝わったと考えられています。稲作が日本に伝わったのは約3000年前のことです。それくらい古くから、すしは作られてきたのかもしれません。日本に残る最も古いすしの記録は『養老令』(奈良時代・718年)。少なくとも1200年以上の歴史のある食べ物なのです。
すしは「なれずし」と「早ずし」に分けられる
すしは、作り方によって「なれずし」と「早ずし」に大きく分けることができます。「なれずし」は一緒に漬けこんだ米飯の発酵によって生じた乳酸の酸味を味わうもので、発酵ずしとも呼ばれます。乳酸菌による発酵のため、出来上がりまで時間がかかります。一方、「早ずし」は食酢を添加して外から酸味を与えたものです。菌による発酵がないため、早く食べられます。
冷蔵技術が全くない時代、日本人にとって食べ物の保存方法は、主に塩蔵か乾燥か発酵でした。なれずしにしても、早ずしにしても、乳酸あるいは酢で食品のpHを下げ、保存性を高めます。人々は、長い時間をかけて、食品を保存する技術を発明し、進化させてきたのです。
多くの日本人がイメージするお寿司といえば、握り寿司でしょう。ごはんに酢を合わせて握り、刺身などの寿司ネタをのせたもので、発酵という要素はありません。短時間で作れる「最も早い」お寿司です。お寿司の歴史というのは、自然発酵で時間をかけて「発酵・熟成(なれ)」させていたものを、少しずつ、短時間で、「早く」食べられるように変わっていった歴史なのです。
平安・鎌倉時代に広く普及した「なれずし」
ここからは、それぞれの時代のすしの特徴と歴史的な変化を取り上げます。
なれずしは、稲作とともに北九州から日本に伝わりました。平安時代の文献『延喜式』(918年)をみると、当時のなれずしは、諸国の特産品として税金のように納められる貴重なものでした。アユやフナ、ビワマスなどの川魚もあれば、アワビやホヤなどの海の幸を使ったなれずしもあったそうです。
鎌倉時代後期の文献『沙石集』(1280年頃)に、奥州(東北地方)の百姓がアユのすしを漬けたという記述があります。なれずしは東北地方にまで広く普及し、鎌倉時代には、百姓庶民にも作られるほど、日常的なものとなりました。
保存食から「なまなれ」という料理へ
室町時代になると、なれずしは「生成(なまなれ)」という形に変化します。なれずしは、元来、魚の保存食で、漬け込んだ米飯を食べずに捨てます。動物性タンパク質である魚が貴重だったからこそ、漬け込んだ米飯以上の価値がありました。
しかし、お米の生産量・魚の漁獲量が増え、日常的に手に入るようになると、保存食の価値は下がります。漬け込んだなれずしを換金したり献上したりするのではなく、自分たちで食べるようになると、
「漬けてそんなに日が経ってないけど、今日食べるものがないから一つ樽を開けてしまおう」
「米飯を捨てるのはもったいない。一緒に食べてしまおう」
そんなことを考えたであろう庶民により、ご飯がある程度酸っぱくなり、魚にもそこそこの酸味がうつったら、まだそれが『生々しい』うちに食べるようになりました。これを「生成(なまなれ)」と言います。

『なれずし』と『生成』を区別するために『ホンナレ』と『ナマナレ』と表現することもあります
なまなれは、発酵期間が短縮したことよりも、漬け込んだご飯を食べるようになったことが革命的な変化だと考えられています。つまり、食資源が豊かになると、すし元来の貯蔵性、保存食という性質から、酸っぱい飯と魚を一緒に味わう料理として扱われるようになったのです。
なまなれの改良型
なまなれのすしとして、米と魚を一緒に味わう食べ方が広まり、様々な工夫が施され、各地で改良型が作られるようになりました。
糀を混ぜる「いずし」
【乳酸発酵の化学式】C6H126 → 2CH3CH(OH)COOH
ごはんを乳酸発酵させるには、お米のデンプン質をバラバラにしてブドウ糖にする(糖化)必要があります。乳酸菌には、デンプンを分解することができる能力を持つ種類がいて、まずお米のデンプンをブドウ糖に分解し、そこから乳酸発酵で乳酸を作っていきます。
ここで、乳酸菌よりも、デンプンの分解が得意な米糀(麴菌)を混ぜて時短することが考えだされました。麴菌は、味噌やしょうゆ、甘酒、お酢などさまざまな発酵食品で使われています。この方法でつくられた発酵ずしを「いずし」と言います。主に、北陸・秋田・北海道などの日本海側、寒い地域で発達しました。気温が低いからこそ、通常の作り方ではなかなか発酵が進まないため、考案されたと考えられています。
いずしは、なれずしに比べて、糀由来の甘味が多く、水っぽくて、食べやすいです。また、馴れが浅いため、魚の生臭さを防ぐために、野菜や香辛料を一緒に入れます。今でも残っている有名なものをあげると、石川県(加賀)のかぶらずし、福井県のニシンずし、秋田県のハタハタずし、北海道のいずしなどです。

とば屋酢店でも、ニシンずしを漬けております。大根と北海道産身欠きニシンを自家製米糀で漬け込んだ文化庁の100年フードにも認定されている若狭の伝統郷土料理です。酒井店限定・冬季期間限定商品です。
酒に漬ける・酢をかける
室町時代になると、お酒やお酢も多く作られるようになり、すしの調理にも使われるようになりました。魚だけを酢に漬けて、米飯は自然発酵をまつものや、できあがったすしにお酢をふりかけるもの。いろいろなナマナレのアレンジが作られたようです。
江戸時代中期の『料理網目調味抄』(1728年)によると、『よく洗った魚を古酒に一晩たっぷり漬けてから、魚の腹にご飯と塩を詰め、桶に詰めて数日馴らす』という作り方が載っています。わざわざ古い酒を使っているのは、古酒の方が酸っぱくなるからでしょう。
酒を混ぜたナマナレは、ごはんのデンプンが乳酸に変わっていくのと並行して、酒のアルコールが酢酸に変わっていった可能性が高いです。江戸時代のなまなれの多くは、お酢の酢酸のにおいを放っていたと考えられますし、発酵による乳酸の酸味から、酢酸の酸味に舌が慣れる土壌が整えられていったのだろうと思います。
発酵ずしから「早ずし」へ
江戸時代になると、なれずし・なまなれなどの発酵ずしから、お酢で酸味をつける「早ずし」に変化します。江戸初期(1700年頃)から京都や大阪で、サバの棒ずしや大阪のバッテラなどにあたる姿ずし・箱寿司が作られるようになります。魚と飯の両方に酢を当てて一両日漬け込むもので、箱寿司は古風な発酵ずしから近代的な早ずしに移る最初のすしと考えられています。
発酵ずしの場合、米飯の乳酸発酵による乳酸味ですが、早ずしは、お酢のツンとした酸味で、味わいのまったく異なる料理です。また、発酵期間が短くなると、魚の骨は柔らかくならず、邪魔になります。そのため、事前に骨を取り除いたり、卸し身にして漬けるようになり、やがて、生の魚が好まれるようになりました。
大阪浪花の杉野権兵衛が書いた『鮓飯秘伝抄』(江戸後期・1802年)の本には、33種の料理ずしが詳しく書かれていますが、フナずしなどの純粋ななれずしについて、「作り方も聞かないし、食べたこともない」とハッキリ書かれているそうです。逆に紹介されているのは、コケラずし、起こしずし、サバずしなど、発酵しない早ずしばかり。せっかくなので、箱寿司の代表的なコケラずしと、若狭のサバずしの記述を抜粋してご紹介します。
コケラずし
上等は鯛、アワビ、松菜。中、下等は赤貝、薄焼玉子、キクラゲ、栗、 竹の子、椎茸、ミツバを貼る。飯は白米一升に水一升、塩五勺の割にする。冷えたらすし箱に詰め、酢をふる。蓼、山椒、生姜を薬味にする小倉ずし、千倉ずし、わかさずし、淀川ずしなどの多くは中下のコケラずしである。
サバずし
北サバ(若狭、丹後より)か熊野サバを塩出しし、骨皮をとり、酢飯を腹に詰め飯と魚を交互に詰めて押し、飯の酸味が魚に移ったらとり出し、外側の飯粒をのけ、腹の飯は共に食べる。今井ずしはこれと同じである。朝に漬け夕方食べる。
「握り寿司」の大流行
江戸時代後期になると、握り寿司が登場します。この握り寿司を大成させたのは、華屋与兵衛です。華屋与兵衛は、岡持ちで握り寿司を売り歩き、やがて屋台を、その後「與兵衛鮓」という店を開きました。ほかにも、高級寿司店の「松がずし」があり、この両店が大繁盛したことが、江戸の寿司事情を一変させました。
握り寿司が誕生したころ、米酢は着物の染色に使われて不足気味でした。そこで、華屋与兵衛は、半田の粕酢(赤酢)に目を漬け、握り寿司に積極的に活用しました。
当時の握り寿司は、今のサイズの2倍以上の大きさで、おにぎりのような感覚で食べられていたのではないかと考えられています。また、寿司ネタは、生ではなく、酢に漬けたり、醤油にくぐらせたり、火を通したり、調味料で煮るなどして下処理を施していました。
早ずしなら味を馴染ませるのに2~3時間はかかるところを、さらに「早く」、すぐにつくることができるようにしたのが握り寿司です。酢飯の上にネタを乗せて手で握ればすぐに食べられる即席ずしは、画期的な早さで江戸市中に広まり、関東大震災や終戦を経て、全国へと広まっていきました。
握り寿司の流行に大きな影響を与えた半田の粕酢
粕酢とは、酒を搾って残った後の酒粕から作ったお酢です。実は、粕酢自体は、奈良時代にも造られていました。しかし、握り寿司の流行を後押しした愛知県半田の粕酢は、それらと一線を画したもので、いわゆる「赤酢」と呼ばれるお酢です。
江戸時代、愛知県のあたりでは酒造りが盛んで、酒造りの副産物である酒粕が大量にありました。この酒粕を活用できないかと粕酢造りに挑戦したのが、ミツカンの創業者、中野又左衛門です。もともと中野家は造酒家であり、酒粕からお酢ができることを経験的に知っていました。
半田で開発された粕酢は、熟成された酒粕を原料にしています。一定期間寝かせた酒粕は、デンプン質がブドウ糖に、タンパク質がアミノ酸などの旨味成分に分解され、メイラード反応によって赤みがかった色合いとなります。この古粕の圧搾汁をもとに、酢酸発酵を進めることで、半田の粕酢が出来上がります。
中野又左衛門は、赤酢を大量生産し、船で江戸に運んで出荷しました。熟成した酒粕を原料に使うことで、甘み、旨み、香りが醸し出されます。また、酒造りの副産物である酒粕をもとに造っているため、米酢に比べて安価。安く仕入れることができて、味もよくなるということで、江戸の寿司職人に広まっていきました。
まとめ
技術の進歩によりお米やお酢の生産量が増えたこと、日本全国、さまざまな環境で食べられるようになったこと、新しい酢が開発されたこと、海運が発達したこと、人々の嗜好が時代とともに変わったこと。さまざまな時代背景のもと、すしは進化してきました。
この記事では、江戸の握り寿司までの歴史を取り上げましたが、それ以降も、回転寿司や海外のカルフォルニアロールなど、さまざまなお寿司へ進化を続けています。これからも、寿司は、多彩に複雑に進化していくことでしょう。
私たちもお酢屋として、寿司の発展をこれからも支えていきたいと思っています。たとえば、とば屋酢店ではさくら酢というフレーバー付きのすし酢を販売しています。春の香りという新しい側面をもった寿司で、春の祝いの席を季節感ある華やかなものにしてくれます。日本人に古くから愛されてきたお寿司を、さらに、わくわくするような食経験に。その想いで、これからも酢造りに邁進していきます。
【参考文献】
篠田統著『新装復刻版すしの本』柴田書店【ISBN:438835189X】
日比野光敏編『すしの絵本』農山漁村文化協会【ISBN:9784540062162】
赤野裕文著『お酢・お寿司検定公式テキスト』日本能率協会マネジメントセンター【ISBN:9784800592385】
丸井ほか『内陸国ラオスの塩と魚で作る伝統発酵食品』日本海水学会誌, 2018, 72 巻, 5 号
![]()
中野 貴之
酢醸造家/(株)とば屋酢店 第13代目
「お酢のことならなんでもご相談ください」がモットー。お客様に「また使いたいと思っていただけるお酢」をお届けできるよう社員と力を合わせて精進中。セミナー講師も時々お引き受けします。